最新の『Steam Deck OLED』の限定版である「ホワイトカラー」を中古で入手しました。実は初代『Steam Deck』も以前所有しており、いろいろといじり倒したのですが、それにならってこちらのマシンも改めてカスタマイズしていくことに。何はともあれ、最初にやらなければいけないと考えたのが、内蔵のSSDを1TBから2TBにすることでした。
以前の『Steam Deck』でも同様のことはやっていたものの、1年半ほど前のことですっかり記憶が忘却の彼方に。改めてこのOLEDで情報を検索してみたところ、微妙に異なっている部分があることもわかりました。また、実際にやってみて引っかかったポイントもいくつか発見することができました。ということで、こちらの記事では『Steam Deck OLED』のSSD換装方法についてご紹介してきます。
最初に準備しておいたほうがいいもの
『Steam Deck OLED』のSSDを交換する前に、用意しておいた方がいいものがいくつかあります。最も重要なことですが、『Steam Deck OLED』に対応しているSSDは、「片面のM.2 2230」です。今回は、ウェスタンデジタルの『SN740 NVMe SSD』を入手しました。

後は主に本体を開けるためのツール類になります。『Steam Deck OLED』のケースと中のネジは、すべてT6サイズのトルクスドライバーになります。今回は手持ちの複数サイズが入ったトルクスドライバーを使用しましたが、可能ならば磁力があるものを選んだ方がいいでしょう。
というのも、結構ネジのサイズが小さいものがあり、外すときはともかくネジを付けるときに若干苦労してしまったからです。
●Kingsdun t6ドライバー トルクスドライバー トルクスT6 精密ドライバー 磁石付き(499円)
https://amzn.to/4e7lp5c

また、ケースをこじ開けるときに使用するオープニングピックやスパッジャー、ケーブル類を外すときに使うピンセットなども用意しておくと安心かもしれません。
●サムコス スマホ修理ツール(535円)
https://amzn.to/4l2QBEJ

また、SSDを交換した後でSteamOSをリカバリーするという作業が入ります。実は以前同様の作業をしたときは、USB Type-AとType-Cの両方に対応したUSBメモリーを使用していました。しかし、microSDカードでも問題ないことに加えて、むしろ充電しながらリカバリー作業も行えるためそちらのほうを推奨します。
今回は32GBのものを使用しましたが、それほど大きな容量は不要で8GBほどあればOKです。ただし、速度が遅いものを選ぶとトラブルに見舞われることもあるようなので、なるべく速いmicroSDカードを用意することをオススメします。
バッテリーをストレージモードにしておく
SSDの交換作業を行うときや、長時間本体を使用しないときなど、安全性を高めるために用意されているのが「バッテリーストレージモード」です。
やり方はとっても簡単で、電源をオフにした後で音量アップのボタンを押しながら電源ボタンを長押しします。BIOSメニューが表示されるので、十字キーで「Setup Utility」にカーソルを移動してAボタンを押して選択しましょう。

画面左側にメニューが表示されるので、その中にある「Battery Storage mode」を選択して「Yes」を選ぶと「バッテリーストレージモード」になり電源が切れます。「バッテリーストレージモード」を解除するときは、電源アダプターを接続しましょう。

トルクスドライバーとツールでケースを開ける
本体背面側にネジが8本しめられているので、こちらをT6 トルクスドライバーを使用して外していきましょう。このときにmicroSDカードが刺さっていると破損してしまう可能性があるので、抜いておきます。
ちなみに、『Steam Deck OLED』はアナログスティック部分が飛び出しているため、ひっくり返すと安定しにくくなります。そこで、本体のケースを使用することで多少安定させることができます。

次が最難関ポイントとも言えますが、オープニングピックやスパッジャーなどのツールを使って、ケースのフタを開けていきます。これらはスキマにねじ込んでいくイメージですが、開けやすい部分と開けにくい部分があるので、いろいろとためしながら開けていくようにしましょう。

なんとかケースにを開けることができたら、バッテリーを取り外すのですが……これが全く抜けず。とりあえず後回しにして後で外せばいいかと思ったのですが、最終的に外さずに作業してしまいました。これはまったく推奨はできないので、可能な限り頑張って外しておいたほうがいいでしょう。


次に白いロックフラップを上げて、右ボタンのケーブルを取り外します。

次に、マザーボードシールドのネジをT6 トルクスドライバーで外していきます。

このままマザーボードシールドを取り外したいところですが……ケーブルの下側に一部テープでとめられているところがあるので、こちらも簡易的に剥がしておきましょう。

このマザーボードシールド部分を、ケーブルを痛めないように気を付けながら、右側に避けておきます。するとSSDが見えるので、こちらをT6 トルクスドライバーでネジを外すと、取り外せるようになります。

SSDを取り外したら、銀色のシールドを壊さないようにして元のSSDを抜き去り新しいSSDと交換。さらに元のボードにネジで取り付けておきます。後はこれまで分解してきた逆のパターンで元の状態にしていけばOKです。

リカバリーのための準備
とりあえず工作的な作業を終えたら、次は新しく交換したSSDにSteamOSをリカバリーしていく必要があります。今回はWindowsで作業を行っていますが、MacやLinuxでは別のツールを使用するので公式サイトをチェックしてみてください。
●SteamOSの復旧とインストール(公式)
https://help.steampowered.com/en/faqs/view/1b71-edf2-eb6d-2bb3
Windowsの場合は、『Rufus(ルーファス)』というツールを使って、インストールメディアを作ることができます。まずはサイトからツールを入手しておきましょう。合わせて、公式からリカバリーイメージもダウンロードしておきます。
●Rufus (ルーファス)
https://rufus.ie/ja/
●リカバリーイメージ
https://store.steampowered.com/steamos/download/?ver=steamdeck&snr=100601___
ダウンロードが終わったら『Rufus』を起動。「デバイス」でmicroSDカードを入れたドライブを指定。「ブートの種類」と書かれた右側にある「選択」を選び、先ほどダウンロードしたリカバリーイメージを選択しましょう。

ここで「スタート」ボタンを押すと、インストールメディアを作成するための作業が開始されます。だいたい5分から10分ほど掛かるので、のんびりお茶タイムとして過ごしてもいいかもしれません。

SteamOSのリカバリー
インストールメディアができたら、microSDカードを『Steam Deck OLED』にセットします。次に、本体のボリュームを下げるボタンを押しながら電源ボタンを押し続けると、ブートメニューが表示されます。

ブートメニューが表示されると、「EFI Boot Devices」のところにひとつだけ選択肢が出るので、そちらを選んでAボタンを押しましょう。

しばらくするとデスクトップモードが立ち上がり、アイコンが4つ並んでいるのがわかります。ここがハマリポイントになっていました。以前『Steam Deck』のSSDを交換したときや、ほかの人の動画をチェックした時は、たしか左から2番目の「Repair SteamOS Install」を選んでいたのですが、「Proced」を選ぶとそのままウインドウが閉じて作業が進みません。
何度やり直してもうまくいかず、もしかしてSSDの取付け自体に問題があるのではないかと疑っていたのですが、実はそもそも選ぶべき項目が間違っていたのです。ここで選択しなければならないのは、一番右側にある「Wipe Device & Install SteamOS」でした。
考えてみれば当たり前で、まっさらなSSDにリペアもクソもなく、一旦すべて消してインストールし直すということですね。

「Wipe Device & Install SteamOS」を選ぶと、どんどん作業が進んでいきます。途中でアナウンスが表示されたときは、「Proced」を選んでいきましょう。すると『Steam Deck OLED』の初期セットアップ画面にたどり着きます。あとは、初めて購入したときと同じようにセットアップしていけば完成です!


初期セットアップが完了したら、さっそくストレージ容量が増えているか確認してみましょう。実際にチェックしてみたところ、容量が1.8TBに増えていることを確認。これで思う存分いろいろなソフトをインストールすることができそうです。









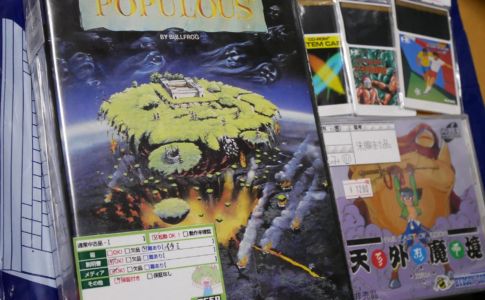







 SummerCart 64
SummerCart 64 WayPonDEV Sipeed Tang Console FPGA レトロゲーミングハンドヘルド 60K
WayPonDEV Sipeed Tang Console FPGA レトロゲーミングハンドヘルド 60K レトロコレクションケースシリーズ 保護 クリアケース スーパーファミコンカセット用 10個
レトロコレクションケースシリーズ 保護 クリアケース スーパーファミコンカセット用 10個



